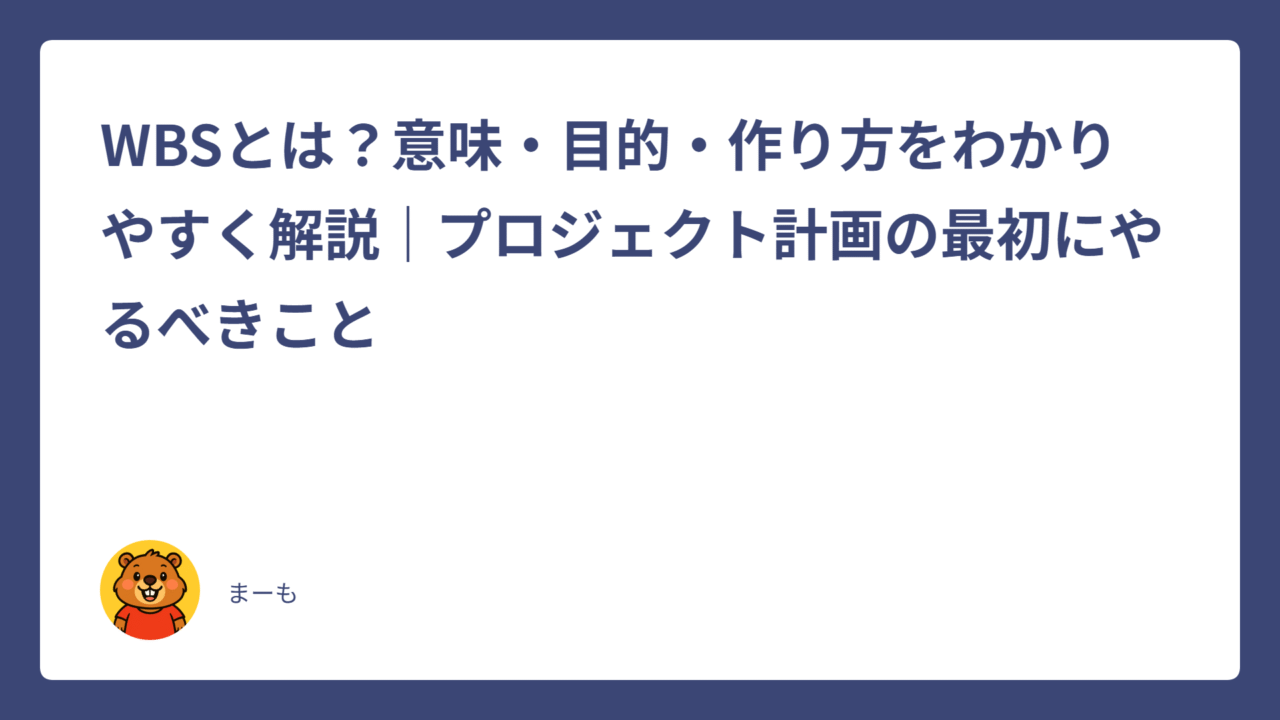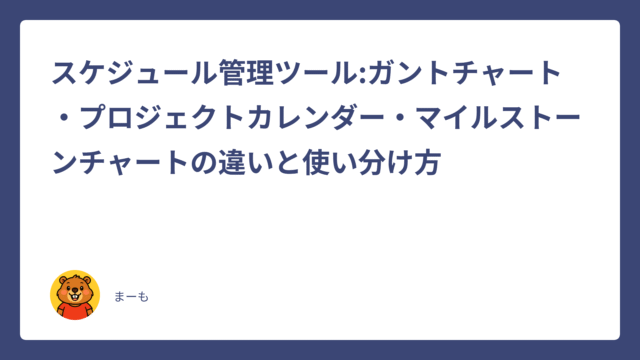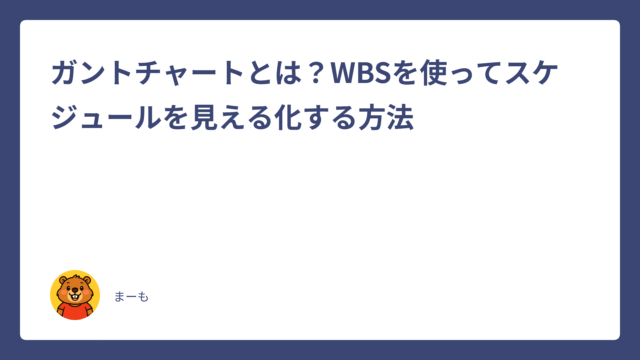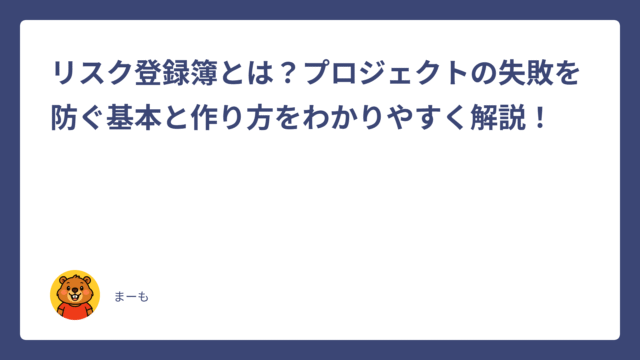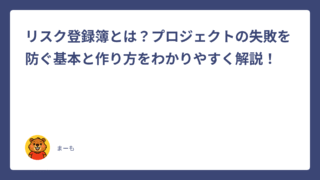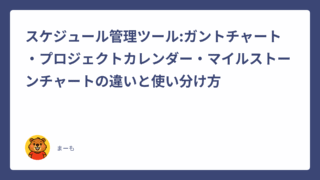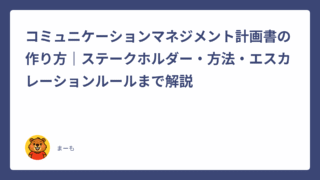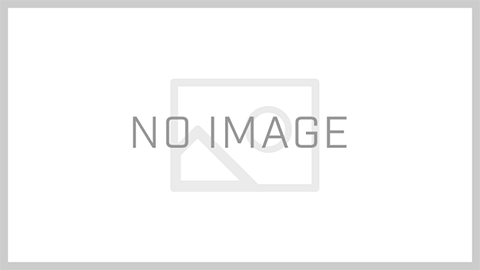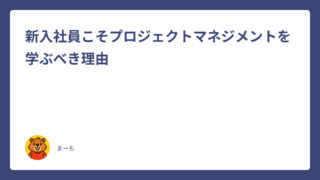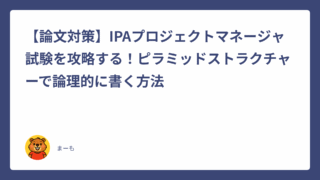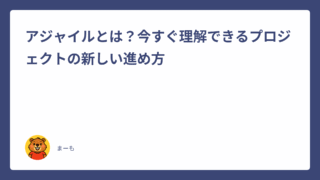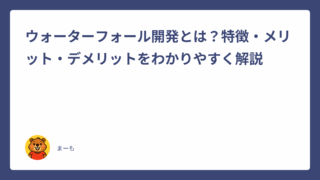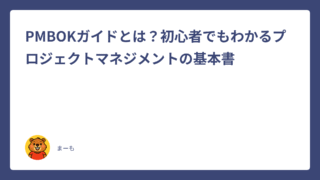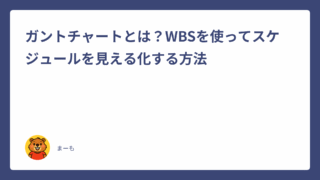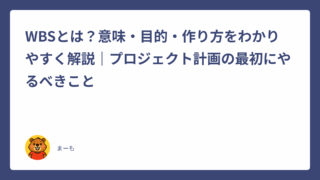プロジェクトを成功させるためには、まず全体像を整理し、抜け漏れのない計画を立てることが重要です。
その出発点となるのが「WBS(Work Breakdown Structure)」です。
この記事では、WBSの意味や目的、作り方のポイントをわかりやすく解説します。
WBSは「作業を要素分解した作業リスト」である
WBSとは「Work Breakdown Structure(ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー)」の略です。
日本語では「作業分解構成図」と呼ばれ、プロジェクトの作業を細かく分解して、構造的に整理するための手法です。
一言で言うと、WBSはプロジェクトの作業リストです。
ただし、単なる箇条書きのリストではなく、上位の目標(成果物)を実現するために必要な作業を階層的に分けて整理するのがポイントです。
WBSを作る目的は「抜け漏れのない計画」を作ること
プロジェクトでは、何を・いつまでに・誰が・どのように行うかを明確にする必要があります。
その最初のステップとして、「何をやるのか(作業の洗い出し)」を明確にするのがWBSです。
WBSを作成することで、以下のようなメリットがあります。
- 作業の抜け漏れを防げる
- 進捗やコストを管理しやすくなる
- チームメンバー間の認識を合わせられる
- スケジュールや担当割り当ての基礎ができる
つまり、WBSがしっかりしていれば、後の工程(スケジュール、リスク、コスト計画など)がスムーズに進みます。
WBSは「プロジェクト計画で最初に作るもの」
プロジェクトマネジメントでは、さまざまな計画を立てます。
スケジュール計画、コスト計画、リスク管理などがありますが、最初に作るのがWBSです。
なぜなら、WBSがすべての計画の土台になるからです。
WBSで作業を定義しておくことで、
- どのタスクにどれくらい時間がかかるか
- どのリソース(人・費用)が必要か
を明確にできます。
逆に、WBSが不十分だと、後から「やるべき作業が抜けていた」「予定より遅れた」といったトラブルの原因になります。
WBSの作り方の基本ステップ
WBSを作成する際は、以下の手順で行うと整理しやすいです。
- 成果物(ゴール)を明確にする
まずは、最終的に何を完成させるかを定義します。 - 成果物を構成要素に分ける
大きな成果物を、中間成果物やタスク単位に分解していきます。 - 作業単位まで要素分解する
実際に担当者が作業できるレベルまで細かくします。
目安として、1人が数日〜1週間で完了できる程度の大きさが理想です。 - 階層構造で整理する
親子関係(大項目→中項目→小項目)の形で構造化します。
ツリー構造や表形式で整理するとわかりやすいです。
まとめ:WBSはプロジェクト成功の出発点
WBSは「作業を要素分解して構造化した作業リスト」であり、プロジェクト計画の最初に作る最重要ドキュメントです。
しっかりしたWBSがあれば、スケジュールやリスク管理もスムーズになり、チーム全体の認識も一致します。
まずはゴールから逆算して、作業をひとつずつ分解していくことが、プロジェクト成功への第一歩です。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。